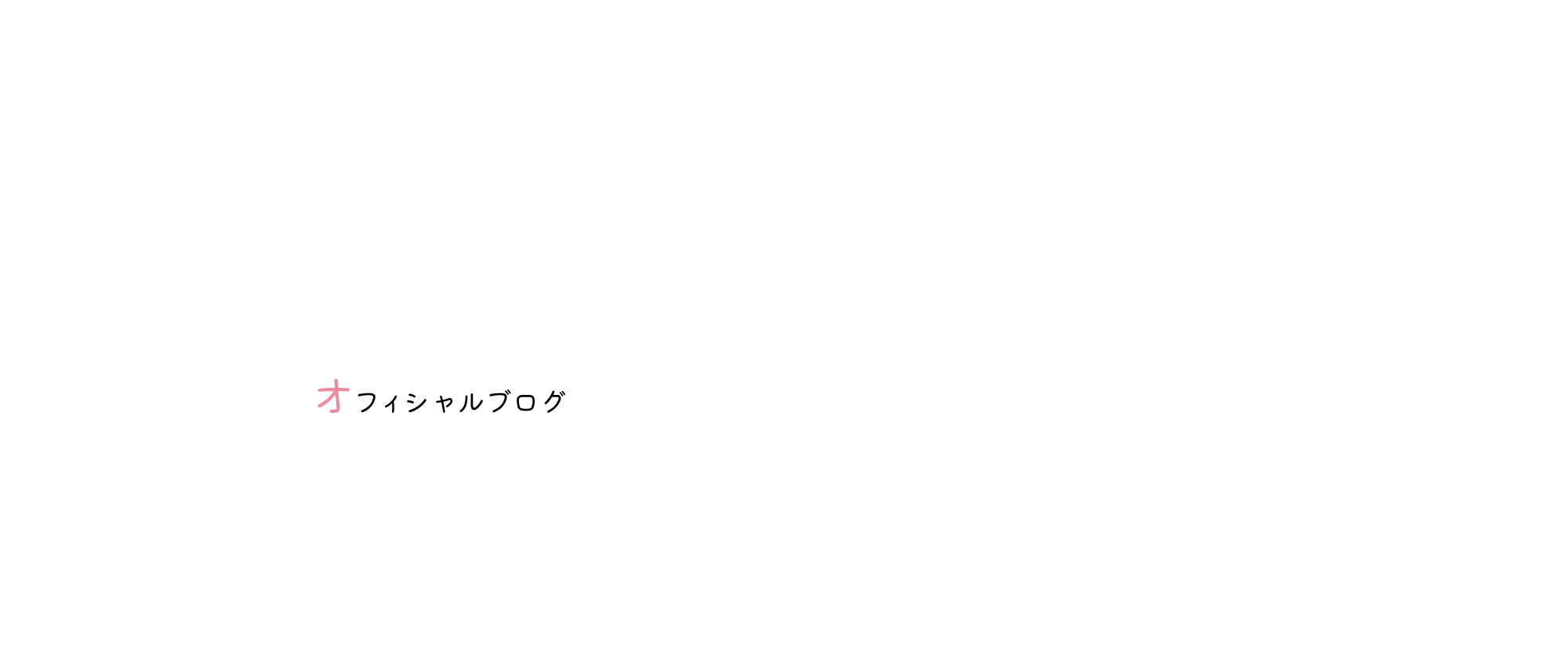
カテゴリー別アーカイブ: 日記
俺の意見より妻の機嫌【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
会社の社長ってどんな印象でしょう?
社内で部下に指示を出して
普段何をやっているかわからなくて
偉そうに見える?
自分の意見が通って
何かあれば権限を行使して
自分の思い描く道筋を辿って
いかにも!みたいな?
もしかしたら
ミスは部下のせい
成功は自分のおかげ
吾輩はスーパーマンなり?
結論、そんなことはないぞ
ステークホルダーが増加し
自分のペースで進まないことの方が多い
他者、他社に振り回されないように
内製化して地力をつける
その過程で指示を出し
目標を立てて追いかける
部下の上には上司がいて
上司の上には社長がいて
社長は会社の外
市場で戦っている
意思決定の変更は
社長の機嫌や気分ではなく
市場の変化を捉え潮流を読んでいるからだ
まあ人間だ
たまに機嫌で判断することもあるだろう
知らんけど
しかしながらどの社長にも変わらない想いがある
火傷させてはいけないから普段は抑えてるんだ
辛く苦しい経験
困難で自分の力が及ばなかったこと
それらで人が変わってしまったケースもある
私が私でいられ続けているのは…
時間だ 今日はここまでとしよう
☆写真を貼ろうと思ったが職員の集合写真がないことに気付いた
また今度撮りましょう
生きるをえがくと語りだす
ながを
ステルス厚意【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
最近よく感じる
ステルス厚意(私が勝手に言ってる)
本当に感謝している
自分の立場から考えると
厚意には厚意で返さなければならないし
愛には愛で応えようではないか
しかしながら私の注いだ愛情に答えてもらわなくても結構
私がやりたくてやっているのだ
…何の話?
職員の前やブログで偉そうに
大きな目標や理想を語ることがあるが
そのプロセスが歩めているのか?
行動が伴っているのか?
と自省することが少なくない
現実をみて共感を得て
気持ち良くなっていないか?
高みを目指し頭を打ってなにくそ!
という姿こそが私ではなかったのか?
自分に求めることを増やす
他者に求める基準を上げる
愚痴は聞かない、意見を聞く
悲観的になることはない
必ずいい未来が待っている

生きるをえがこう
ながを
知識はこの世で最も尊い宝である【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
最近よく使う○○だが○○、ですが
私がサービス管理責任者になった頃によく読んでいた
ビジョナリーカンパニー2 飛躍の法則 に出てくる
第5水準のリーダーのところで
”二面性”と表現されています
コリンズは第5水準のリーダーの特徴として
”個人としての謙虚さ”と”職業人としての意思の強さ(不屈の精神)”
一見矛盾する”二面性”を兼ね備えていると挙げています
こうあるべきだ、という理想論ではなく
偉大な企業へと飛躍した企業群とできなかった企業群を
比較検討した結果、導き出された観察事実とのこと
一時期はまって2周読みましたが
あかん、記憶が薄れている、読み直そう
そしてリーダー達に読ませよう…?!
最近見直したのは
優しさと甘さを区別
厳しさと恐怖を区別
というところか
☆頑張っている皆さん、お疲れ様です
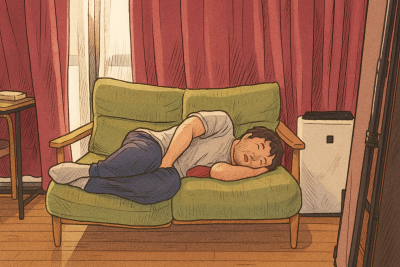
生きるをえがくと第5水準のリーダーになれる?!
ながを
来た道戻るの大嫌い【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
全世代総力結集で全員参加で頑張らないと立て直せない
人数少ないし全員に働いていただきます
ワークライフバランスという言葉を捨てる
働いて働いて働いて働いて働いてまいります
高市さんの言葉です
賛否両論あるようですが
メッセージ性が強くわかりやすい
私は妙に共感したのと
ランチェスターの法則が思い浮かびました
世界に目が向いているのだなと勝手に感じました
もう一つ
ワークライフバランスは仕事と生活の調和です
”仕事以外の生活との調和を取り両方を充実させる働き方、生き方”なので
正しくはワークライフバランスを見直す、ではないかと思いました
どこにひっかかっとんねん、とツッコまれそうですね
そんな概念すら必要ないということなのでしょうが…
☆馬車馬のように働くか…
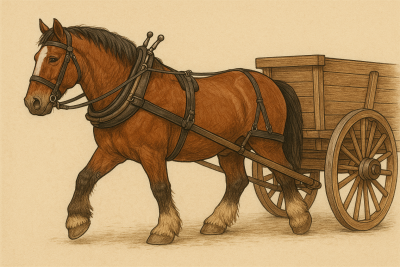
生きるをえがく
ながを
楽天的な虎【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
動物占いやってみた 以下、結果と感想
『あなたの基本性格』
「楽天的な虎」タイプのあなた。
あなたは誰にでも包み隠さず自分をさらけ出して付き合いますし、平等な態度で接するはずです。
⇒さらけ出せているのか?!
相手を見て差をつけた接し方をするのは好まず、分け隔てない接し方をしているでしょう。
⇒そうでありたいものです
自分には厳しくても、人には全てを許す寛大な心を持っています。
⇒全ては許せませんよ
ただ、断りきれない弱さも、少なからずあるかもしれませんね。時には、自分を優先することも大事です。
⇒そうします
いつまでも人を一番に考えていると、あなた自身が疲れてしまいます。断ると嫌われるのではないか、と考えてしまうかもしれませんが、そのような心配は無用です。
⇒悩み相談になってる?
いつも人のために動いているあなただから、時には自分を大事にしても、誰も文句など言いません。
⇒ほ~
ずっと変わらず、愛され続ける人気者なのです。
⇒どうやら人気者らしい
某職場では動物占いの結果を採用時の参考にしているとか?
(うちではありません)
何となくやってみましたがその他にも気になる項目がありました
皆さんも興味があればやってみて下さいね
☆二人とも立ち歩いて転んでおでこに青たんをつくっている
成長には痛みが伴う ということか?

生きるをえがく
ながを
実るほどに頭が下がる【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
総裁選を終え
高市早苗さんが選ばれましたね
高市さんの政策の中には物価高対策
中小事業者や病院、介護施設、生活者に寄り添う対策
というものがあります
某youtube番組で
「エッセンシャルワーカーの処遇を改善する」
「特に福祉従事者は27年の制度改定を待たずに実施する」
などと仰っていました。(都合よく受け取っていたらすみません)
我々の立場としては期待して待ちたいと思います。
福祉は今後ますます質が評価され
業界として質を上げる為に努力をするいい機会となります
税金が財源ということは常に意識しておかなければなりません
様々な民間事業者が業界に参入する中で
「営利法人は…」等と後ろ指を指されないよう
堂々と我々の力を発揮していきたいものです
今後、日本初の女性総理大臣は?と問われると
高市さんの名前が挙がるでしょう
これは事実なので当たり前ですが…
質の高い福祉事業所は?と問われた時
”ラボ”と名前が挙がるよう
第一想起を目指さなければなりません
ま~た長尾が語ってるわと言われそうなので
今日はこの辺りで…
☆過去にレクで行なったサッカー
ラボでは初めての企画でした

生きるをえがく
ながを
二律背反【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
私は感情的な人間ですが
社会に出てから論理的に物事を考えるようになりました
これは当時の上司や先輩の影響が大きそうです
影響というか想いだけで議論に挑み粉々にされ
論理でも負けたくないと
学習するようになったのだと思います
そんな私だからか
最近は矛盾や二律背反に興味があったり
○○だけど○○のような
成立しないはずなのに成立しそうなものに惹かれたり
感情と論理の両立を目指している?ようです
以下に並べるのは○○だが○○ですが
これらは成立するものですので
目指したいと思います
・寛大な性格だが、細部をないがしろにしない厳格さがある
・柔和で穏やかだが、ここぞという時はテキパキと物事を進める
・自分にも人にも厳しいが、横暴な態度はとらない
・何か問題が起きたら先頭に立って事を納めるが、普段は目立たず慎み深い
・静かでおとなしくしているが、芯があり自分の信念に反することには毅然とした態度をとる
・歯に衣着せずものを言うが、人当たりは温和で威圧感を与えることはない
・大まかに物事を捉えるが、杜撰ではなく筋道がしっかりしている
・意思が強く剛毅な性格だが、押しつけがましくなく思慮深い
・実行力はあるが、暴走せず道理をわきまえて行動する
以上
私こそ生きるをえがく真っ只中だ
☆仕事は好きだが、家族のもとへ帰る

生きるをえがく過程/家庭
ながを
反省はするが後悔はしない【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
生きるをえがくために意思決定支援は外せません
意思決定の優先順位は以下のように言われています
1.本人が出した希望
2.支援を受けつつ本人の意思に基づく選択、決定
3.(最終手段としての)最善の利益による代理決定
ラボでは何かを選ぶ機会が少しずつ増加しています
意思決定に必要な要素を以下羅列
・失敗する権利を奪わない
・パターナリズムの危険性
・リスクマネジメントとの線引き
命に係わる場合は「レスキューモデル」で他者が決定
日常生活は「エンパワーメントモデル」で本人の経験を重視
悩み苦しむことも
葛藤し迷うことも
上手くいったことも
様々な経験機会があることも
生きるをえがくに必要な構成要素
☆本日の伊藤職員
金髪カツラに帽子(利用者さんのもの)
カラフル手ぬぐいに歯のTシャツ
独特な生きるのえがき方だな…

生きるをえがくと味が出る
ながを
熱を失ったときに老いる【西宮市 ラボ 生活介護 強度行動障害】
生きるをえがく
長尾です
SNSを開始してからはや7カ月
5月末からはほぼ毎日投稿し
SNS総フォロワー数は2000人を超えました
凄いような物足りないような…
さらば青春の光 森田さんが言っていました
「”こいつ誰やねん”って思わせるのが最初の勝負」
TikTokとInstagramの視聴数は累計1600万
プロフィールアクセス数は累計10万
これだけの人数にこいつ誰やねん?と
思ってもらえたのかもしれません
伝えたい想い
利用者さんや職員の魅力、頑張り
今後も発信していきます
”福祉社長の長尾”TikTokとInstagramでは
職員の人柄や雰囲気を感じてもらえるでしょう
今後はXで福祉の時事ネタについて
コメントする予定です
かみんぐすーん?
そしてラボのInstagramでは
利用者さんの活動が紹介されています
いつまでも最初の勝負をしていてはいけない
次の勝負だ

(この写真の元データはラボのInstagramでUPしてくれるはずです)
生きるをえがくと魅力が溢れる
ながを


